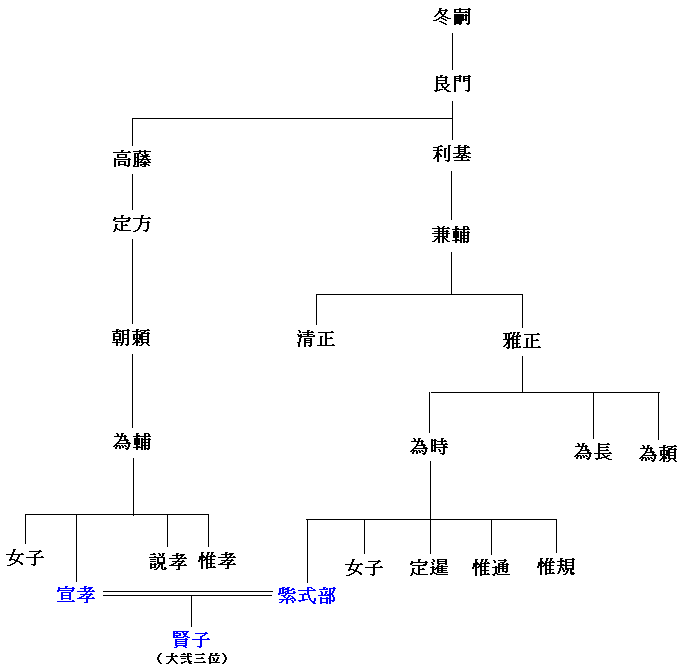紫式部について
『源氏物語』を執筆したと言われている(未だ諸論分かれていて定説ではないが)紫式部。彼女はなぜあのような膨大かつ偉大な作品を執筆することができたのであろうか?この疑問の解明に少しでも近づくためにも、彼女の一生を知ることは重要であろう。そこで、ここではすでに彼女についての様々な文献(赤木志津子氏・今井源衛氏・清水好子氏・岡一男氏など)が出版されているので、それらを参考に、できるだけ分かりやすく簡略的に、紫式部の一生を解説していきたいと思う。よって、ここで説明している以上に知りたい方は、それらの文献に当たってもらいたい。また、最後に系図も掲載しているのでそちらも参考に。
(1)出生
紫式部の出生については、ほとんど分かっていないというのが実状である。それどころか、本名も判然としないし、本当に『源氏物語』を執筆したのかすら分かっていない。それと言うのも、現代のように作品を執筆する際に作者名を公表することなど当時にはないことだからである。しかしながら、幸いにも紫式部には日記『紫式部日記』があり、ここの記事から『源氏物語』の作者が、おそらく紫式部であろうことが分かる。もちろん絶対ではないが・・・。さらに、この日記から紫式部の出生年もある程度予想することができるがはっきりとはしていない。現在までに予想された出生年は4説ある。
① 970年説……今井源衛(『人物叢書 紫式部』)
② 973年説……岡一男(『源氏物語の基礎的研究』)
③ 975年説……与謝野晶子(『紫式部新考』)
④ 978年説……安藤為章(『紫女七論』)
以上がその説であるが、現代では今井説もしくは岡説が有力であるようだ。しかし、もし今井説が正しいということになると、今まで紫式部の兄と見られてきた惟規が弟ということになる。いずれにせよ、このあたりが紫式部の出生年と考えて良いだろう。
(2)家系
紫式部は、当時の代表的な文人で、後年国司を歴任した藤原為時の娘である。為時の祖先をたどってみると、藤原冬嗣ぐにつながる摂関権門の藤原北家と同族であるが、『古今集』時代の歌人として名高い曾祖父の藤原兼輔(中納言)以外は四・五位どまりの中流階級の家柄であった。
それでは、家系上の重要人物を個別に見ていくことにする。
○ 藤原兼輔
兼輔は、中納言という身分でありながら、その娘の桑子を醍醐天皇の更衣として奉ったり、また勅使として宇多天皇のお見舞いに上ったり、伊勢斎宮に赴いたりしているところを見ても、よほど天皇の信任が厚かったものと察せられる。また彼は、和歌の方面でも勅撰集に計四十五首収められたり、『兼輔集』という家集を残したり、後に三十六歌仙の一人にあげられたりしている。そして、彼の邸宅は京極加茂河畔にあったことから、「堤中納言」とも呼ばれていた。紫式部も『源氏物語』の中でたびたびこの兼輔の歌を題材にしている。
○ 藤原雅正
雅正は兼輔の長男で、官位は低かったが、彼の妻は兼輔の親友である定方の娘であった。そして彼も、『後撰集』に七首選ばれ、その中には貫之や伊勢御との親密な贈答歌もある。
○ 藤原為頼
雅正の長男で紫式部の伯父にあたるのが為頼である。彼には家集が一巻あり、また『拾遺集』以下勅撰集に十一首入っている。
○ 藤原為時
紫式部の父為時は、雅正の3男で、菅原文時を師としてその門下に入った文人であった。彼は若くして大学で学び文章生となり、式部丞・蔵人を経て式部大丞に進んだ。また、藤原為信の娘と結婚し、その翌年には長女が、さらに次の年に次女が生まれた。この次女が紫式部である。それから二年後に長男の惟規も生まれた。しかし為時の妻(紫式部の母)は、体が弱かったらしく長男惟規を生むとすぐに亡くなってしまったようである。また彼の官位は、式部大丞に進んだ後九八六年退官することになり、そのまま長い歳月がたつことになる。それから十年後、ようやく越前の国守に任ぜられた。
以上が紫式部の主な家系の人物であるが、まず、彼女の家系は身分的には非常に低い方であったことが分かる。そのことが、おそらく『源氏物語』の登場人物にも色濃く影響を与えているのであろう。その証拠に、作品中では受領階級の人物が際だっている。明石一族などがそうである。また、彼女の家系には文人が多かったことも非常に重要であろう。紫式部の育った環境の全てが、あの膨大な作品を書かせたのであろう。
(3)少女・青春時代
紫式部が『源氏物語』を執筆した要因は、先に見た家系の他にも、彼女自身の送ってきた生活・経験というものが大きく影響を与えていることは間違いないであろう。それは、もし彼女がたとえ文人の揃った環境で育ったとしても、彼女自身が当時の一般的な女性たちと同じ生活を送っていたならば、おそらく『源氏物語』などという作品を執筆する題材など発見することができなかったものと思われるからである。たとえば『蜻蛉日記』を書いた道綱母は、藤原道長の父である兼家と結婚しているし、清少納言も中宮定子に仕えるという生活を送っている。それでは紫式部はどのような生活を送ってきたのか、項目に分けて見ていくことにする。
○ 学才
『源氏物語』を一読すると分かるように、あの作品を執筆するためには多くの知識が必要である。特に中国文学(『史記』や白楽天など)の影響が色濃く見え、彼女がそれらを愛読していたことは明らかであろう。それは、彼女の家系的なものが大きく関係していると思われるが、それだけであれほど知識が豊富になるとは考えられない。やはり、彼女の学才というものがずば抜けていたからであろう。彼女の学才について参考になる記事が『紫式部日記』にある。
この式部丞といふ人の、童にて『史記』といふ書読み侍りし時、聞きならひつつ、彼の人は遅う読み忘るる所をも、怪しきまで敏く侍りしかば、書に心入れたる親は「口惜しう男子にて持たらぬこそ幸ひなかりけり」とぞ常に嘆かれ侍りし。
ここで「式部丞」というのは弟(一説には兄)の惟規である。彼に『史記』を教えていたところ、傍らで聞いていた紫式部が先に覚えてしまったので、父為時が、男の子なら良かったのに・・・、と嘆いている場面である。これを見れば分かる通り、彼女は人一倍暗記力・学才があったということである。これが『源氏物語』の夕霧などに反映されているのではないだろうか
○ 出仕?
紫式部が中宮彰子に出仕したことは有名であるが、与謝野晶子はそれより以前の彼女が十七歳の時に一度出仕していたのではないかと想定している。それは、家集に「童友だちなりし人」という文字があり、それを紫式部が伯父為頼がその役所の次官を勤めていた皇太后昌子内親王のもとに童女(メノワラワ)として奉仕していたころの仲間ではないかということである。しかしながら、これに関しては、今井源衛氏も言及しているが、日記その他の傍証するものがなく、さらに日記では彰子がはじめての出仕であるかのような書きぶりであるので、これに賛成することは難しい。
○ 恋愛
紫式部が藤原宣孝と結婚したことは周知の通り(後に述べる)であるが、彼女が結婚した年齢はおよそ27・8歳の頃と言われている。これは当時で考えると大変晩婚であり、それまで彼女が恋愛を経験していなかったと考えるのは不自然である。そこで彼女の恋愛に関して参考になる記事が家集にある。
方違へに渡りたる人のなまおぼおぼしきことありて帰りにけるつとめて、朝顔の花をやるとて、
おぼつかなそれかあらぬか明けぐれの空おぼれする朝顔の花
この解釈を石川徹氏は、男性と肉体関係をもった翌朝に、彼女が贈った手紙であると解している。そしてこの時、彼女は姉の死の直前である23・4歳であったらしい。つまり、宣孝と結婚する前であることは明らかである。もちろん確証はないが、彼女が28歳頃まで男性と関係を持たなかったと考えるよりも、ここで恋愛をしていたと考える方が自然ではないであろうか。
○ 姉の死
紫式部の青春時代には一つの転機があった。それは994年頃、彼女が25歳頃であるが、この前後に彼女の姉が亡くなってしまう。おそらく当時の流行病であると思われる。紫式部には同腹の女兄弟は姉一人で、生まれてからずっと一緒に暮らしていたので、その存在は非常に重要な人物であった。その証拠に、彼女は姉が亡くなると、他人をその身代わりにして姉君と呼んでいたくらいである。特にこの女兄弟との関係は、宇治の大君と中君にその面影が写されているとも言われている。
○ 越前行
先にも述べた通り、紫式部の父為時は、長い無官時代を経て、996年越前(現在の福井県武生市)の国守に任官された。彼女はそれに同行することになる。弟の惟規は、当時まだ文章生であたために同行はしなかったらしい。それにしても、紫式部は何故に4年間という長い離京を決心したのだろうか。その理由は様々考えられるが、たとえば今井源衛氏は、何らかの男性(後の結婚相手宣孝)との交渉が破綻しつつあったのではないか、と予想している。宣孝は彼女の離京前より結婚を申し入れていたらしく、彼女はそれに気が進まなかったようである。いずれにしても、彼女は越前へ発っていくのである。しかしながら、越前での生活はわずか1年で帰京することになる。その理由は、いよいよ宣孝との結婚の意志が固まったからであろうと考えられる。宣孝は離京中も求婚し続け、そのねばり強さが彼女に結婚に踏み切らせたのであろう。
(4)結婚生活
998年に越前から帰京した紫式部は、まもなく藤原宣孝と結婚する事になる。この時、紫式部は27・8歳で宣孝は45・6歳で、宣孝が17歳程度年長になる。そして二人はいとこ関係にもあった(系図参照)。当時としては、非常に晩婚であったと思われる。それは、母をすぐに亡くしたために、為時一家の母代わりになったことから、結婚が遅れたと考えられる。
夫になった宣孝は、中流階級の官人で、その経歴は備後・周防・山城・筑前等の受領を経て正五位下中宮大進に至った。また性格は、『枕草子』115段「あはれなるもの」などを見ると分かるように、非常に闊達・磊落な性格であったようである。そのため女性関係も多いようだが、宣孝は紫式部と結婚して2年後に亡くなっているので、これらの女性関係はそのほとんどが彼女との結婚以前であったことは間違いない。
ところで紫式部と宣孝との出会いは、いとこ同士であったこともあるが、彼女の父為時と宣孝は以前より知り合いであったことが大きく関係している。そして宣孝は、筑前の任期が終わった995年以後、紫式部が越前に赴いた翌年秋まで1年半ばかりの間と考えられる。この求婚が彼女の単身帰京を決心させた主な動機であるだろう。それから結婚生活が始まったのだが、結婚直後より事件が多発した。まず紫式部の伯父為頼の死、内裏焼失、それから道長の娘彰子の入内などである。999年宣孝は豊前国宇佐神宮(九州地方)の奉幣使に任ぜられた。このころ紫式部は宣孝との間に女の子を生み、賢子(カタイコ・大弐三位)と名付けた。
さて二人の結婚後の関係であるが、紫式部の性格が芯の強い、勝気なものであったために、あまりうまくは進まなかったようである。当時の一般的な妻とは違うところに新鮮さを感じた宣孝であったが、結婚相手としては疲れのたまるような相手であったようだ。そのため、徐々に宣孝の足は彼女から遠のきはじめる。まさに『蜻蛉日記』の作者道綱母と同じ境遇に立たされるのである。しかしながら、もっと不幸な事が起きるのである。それは1001年、夫宣孝が突然亡くなってしまうことである。結婚わずか2年という短い期間であった。宣孝はこの時享年49歳ほどであった。おそらく当時の流行病であろうが、これにより、紫式部は再び一人の人生が始まるのである。
(5)物語執筆
紫式部がいつ大作『源氏物語』を執筆したかはまだはっきりしていない。日記の記述から、1008年(寛弘5年)までには、少なくとも「若紫」巻までは執筆していたようである。それは藤原公任から彼女が若紫と呼ばれている記述である。そして、物語の執筆時期について主に3つの論に分かれている。
1、宣孝と結婚以前ないし結婚生活中
2、宣孝死後、宮仕え以前
3、宮仕え以後
一応以上の3つがその論であるが、安藤為章の『紫家七論』以来、2の寡居時代起筆というのが通説になているようだ。彼女は少女時代からも物語を書く才能があったようだし、夫を失った後、友人を慰めに物語遊びなどをしていたようである。その延長が、あのような大作を生むようになったのではないだろうか。また、後に彼女は中宮彰子に宮仕えすることになるが、これは『源氏物語』を読んだ道長が彼女に宮仕えを依頼したという説があり、これからも寡居時代に書いたという説が有力になる一つの理由がある。しかしながら、実際のところ起筆の時期がいつであるのかははっきりしていないし、これを証明することも難しいであろう。それは、『源氏物語』を執筆したのが紫式部であるということすら、まだ定説にはなっていないからである。
1、藤原道長の加筆説
2、紫式部の父為時が大筋を書き、細部を彼女が書いたという説
3、宇治十帖以下は娘の賢子(大弐三位)が書いたという説
4、匂宮・紅梅・竹河の三帖は別人が書いたという説
これらの説が未だ根強く残っているのである。まず、これらを証明しないかぎり起筆の時期を判然とさせることは難しいであろう。
(6)宮仕えと死
紫式部が中宮彰子に出仕したのは、夫の死後1005年(寛弘2年)12月29日と言われている。このことについて彼女は一首の歌を残している。
身の憂さは心の内にしたひ来ていま九重ぞ思ひ乱るる
この歌を見れば分かる通り、紫式部はこの出仕に対して、あまり乗り気ではなかったようである。おそらく藤原道長の要請により、無理矢理出仕させられたものと思われる。それはやはり、『源氏物語』を執筆したという噂がそうさせたのであろう。
ところで当時の出仕は、紫式部があまり乗り気でなかったことからも分かるように、必ずしも良いことであるとは考えられていなかったようである。実際、彼女は出仕するにあたり、友人から批判を受けているし、『枕草子』にも宮仕えを軽々しい行為と述べている。それは、女房生活ではとりわけ男女関係が乱れやすいことが一番の原因であるらしい。しかし、紫式部は中宮彰子に出仕することになった。これは、対立関係にある道隆の娘定子に清少納言が出仕していて、その文芸的世界に対抗するためであったと思われる。
さて出仕後であるが、その学才ゆえに周囲からは、あまり良い目で見られなかったようである。「日本紀の御局」というあだ名がつけられたことは有名であろう。それで、出仕後まもなく実家に帰ってしまうが、彰子から呼ばれて泣く泣く戻ってくることになる。その後も、周囲は厳しかったようで、彰子に中国文学などの講義を行っていたが、周囲に対しては、自分はボケたように振る舞うことで、その学才を隠していたらしい。
そんなこんなで、日記から1013年(長和2年)秋までは出仕が続いたことが分かるが、その後の消息は不明である。おそらくこの翌年1014年(長和3年)春ごろに彼女は亡くなったという説が現在有力である。今井源衛説では45歳、岡一男説では42歳ということになる。今井説では、晩年の紫式部は、道長に対して批判的になった彰子と藤原実資の間を取り次ぐ重要な役割を担っていたようである。いずれにせよ、それほど長寿ではなくむしろ早逝であったようである。
(7)系図
★ 参考文献
・『紫式部』 今井源衛 (吉川弘文館)
・『紫式部』 清水好子 (岩波新書)
・『源氏物語の基礎的研究』 岡一男 (東京堂)
・『源氏物語ハンドブック』 鈴木日出男 (三省堂)